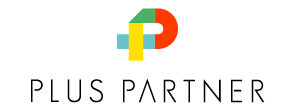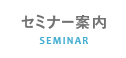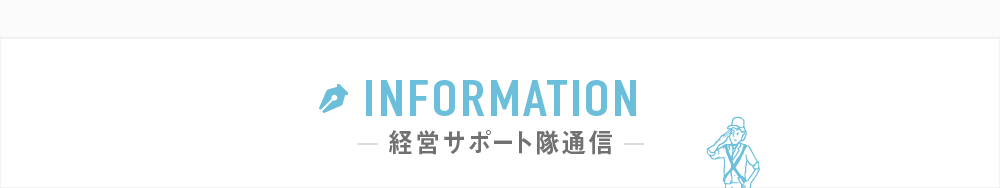Vol.73 2018年1月号
2018年01月01日
お客様の“未来を創るお手伝い”
をモットーに、一同邁進してまいります!
本年も何卒よろしく
お願い申し上げます!!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
新しい年が始まりました!
今年はどんな年にしたいと思っておられるでしょうか?
昨年末に、天皇陛下の退位日が2019年4月30日に決定したことが明らかになりました。
これまで、崩御により承継されていた天皇の地位が、計画的に承継されることになった背景には、様々な事情があろうかと思いますが、やはり、計画的に準備できる方が混乱も少なくスムーズに移行できるというメリットが大きいのではないかと思います。
歌舞伎の世界を見てみますと、大きな名前が代々襲名されていきます。例えば、昨年には松本幸四郎が松本白鸚を、市川染五郎が松本幸四郎を、松本金太郎が市川染五郎を親子三代で襲名しました。
天皇も歌舞伎役者も、長きにわたり伝統を引き継ぎ、また次の世代につなげていくということを繰り返して歴史が守られています。
産業に目を向けますと、AIやIOTなど技術の進歩により、生活は快適になり、一方で人間でなければできない仕事の範囲は狭くなっていくといわれています。それは遠い未来の話ではなく、すぐそこに見えている未来に起こる事実です。
これまでの人間の歴史を振り返りますと、技術革新は18世紀の蒸気機関による機械化、20世紀初頭の電力による大量生産、20世紀後半からのコンピューターによる自動化と進んできました。この先AIやIOTにより、いわゆる第4次産業革命が起こると言われていますが、どのような社会が実現するのかは、まだおぼろげな状態です。
ただ、確かに言えることは、今、私たちは、変革期の真っただ中にいるということです。つまり、どんなビジネスにもチャンスはあるし、どんなビジネスも衰退する可能性があるということです。
天皇や歌舞伎役者のように、準備をして期限を決めて大切なものを引き継いでいくこと、そして、変化の波に飲み込まれず、変化をとらえて自ら変革していくことが、これからの時代を生きていくために大切なことではないかと思います。