2024年12月の金言
2024年12月02日
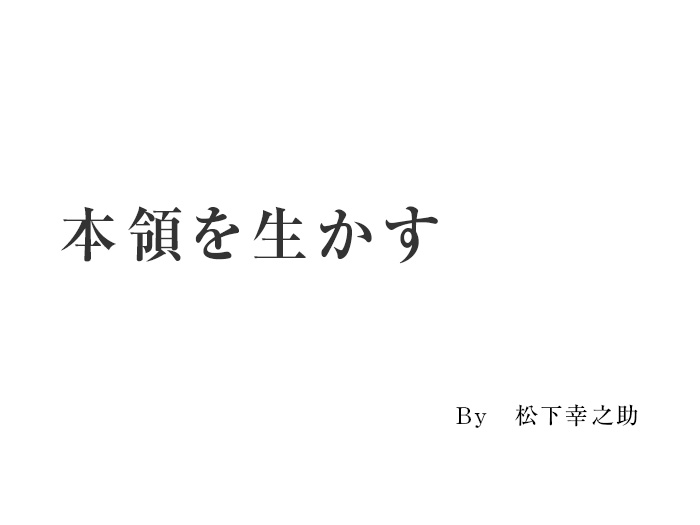
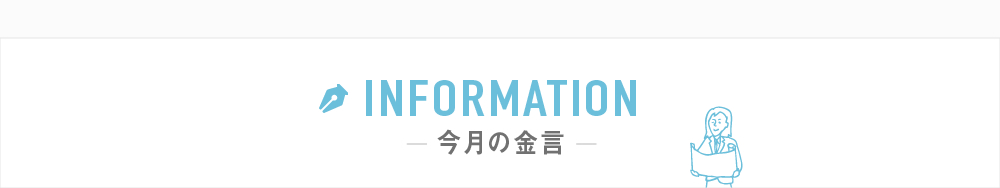
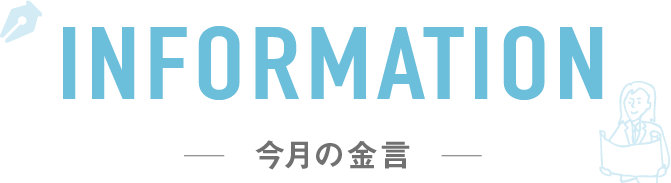
2024年12月の金言
2024年12月02日
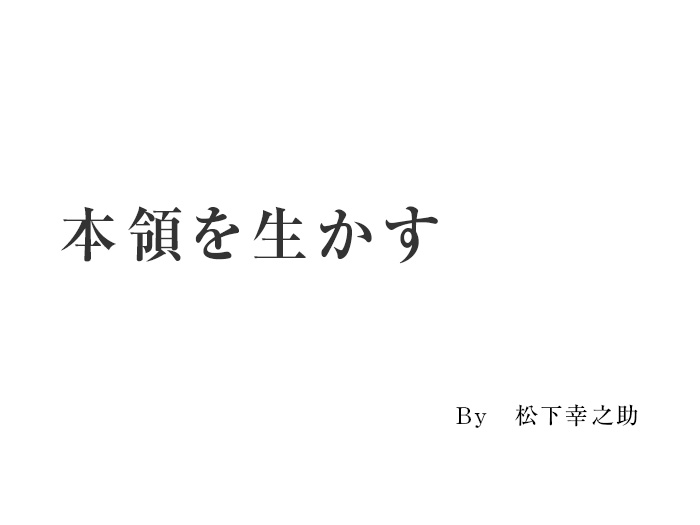
Vol.156 2024年12月号
2024年12月02日
今年もお世話になりました。
皆さまどのような年をお過ごしになりましたでしょうか?
一年を振り返り、来年また素敵な年を迎えられますように!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
今月も「致知」(2024年5月号)より93歳の現役料理人道場六三郎氏の
インタビューを抜粋してお届けします。
『二十代前半の時に、勤めていた神戸のホテルで板長から酷いいじめに遭ったことがあります。調理場の準備はどんなに急いでも二時間かかるのに、開店一時間前まで中に入れてもらえないとか、「遅いぞ、ボケ」と怒鳴られ、殴られたり蹴飛ばされたり、つくった料理をひっくり返される。辛くて心が折れそうな僕を支えてくれたのは両親の言葉でした。(中略)「何も分からないうちは我を出してはいけない。鴨居と障子がうまく組み合わさっているからスムーズに開閉できる。それが合わなくなれば、障子の枠を削る。上の鴨居を削ることはしない。鴨居とはお店のご主人で、六ちゃんは障子だ。だから修行とは我を削っていくことだよ」と。こういう言葉を自らに言い聞かせ、「ここが踏ん張りどころだ。いま辞めてしまったらこれまでの努力が無駄になってしまう」(中略)と心を鼓舞し、いじめや理不尽にへこたれず毎日朝六時から夜十一時まで一所懸命働きました。すると次第に板長の態度が変わり、僕のことを認めてくれるようになったんです。 この時の経験から学んだのは、「環境は心の影」ということです。自分の心のあり方が目の前の環境をつくっている。他人や環境を直接的に変えることは難しいけれども、自分の心や物事の捉え方を変えることで、相手や周りの環境も自ずと変わっていくんです。二十代の時にそのことを経験していたからこそ、独立前の逆境を乗り越えることができたと思います。(中略)
たくさんの料理人を見てきて、伸びていく人と途中で消えていなくなってしまう人の差は、料理の腕以上に日常のあり方に現れるというのが僕の実感です。脱いだ靴を揃える。ドアを開けたら閉める。自分から大きな声で挨拶をする、あるいはお膳を出す時に箸やお皿が傾いていないか確認する。日常の当たり前のことをいかに徹底できているかが問われるんです。
―老いて輝く人、老いて衰える人の差はどこにあるでしょうか?
それはやっぱり、「ありがとう」っていう感謝の気持ちをいつも持てる人、どんな時も笑顔を忘れない人、そして、死ぬまで打ち込む仕事があるってことじゃないでしょうか。
僕は七十五年料理を続けてきて、いまも料理が恋人。料理人になったことを本当に有難いと思っていますし、料理に生かされている人生だなと。料理のことしか考えていないですからね。「交わりは進化なり」と言いましたが、これとこれを組み合わせると、また別の味が生まれる。新しい発見がある。だから料理の道に終わりはない、永遠だなとつくづく感じます。「流水濁らず、忙人老いず」っていう言葉があるじゃないですか。水は流れているから清らかなのであって、溜まると濁ります。それと同じで、人間も動きが止まったら老いると思うんです。昭和の大横綱・双葉山が六十九連勝で記録が止まった時に言った「我、未だ木鶏たり得ず」の如く、生きている限り倦まず弛まずの心意気で、「昨日よりもきょう、きょうよりも明日」と高みを目指していく。何歳になっても人間を磨き続ける。これからもそういう人生を送りたいと心に期しています。』
いかがでしたでしょうか?環境を変えることはできなくても、自分を変えることはできます。しかし、それは簡単なことではありません。あたりまえのことを繰り返し、感謝と笑顔を忘れずに、新しいことにチャレンジし続け、豊かな人生を歩んでいきたいと思いました。
2024年11月の金言
2024年11月01日
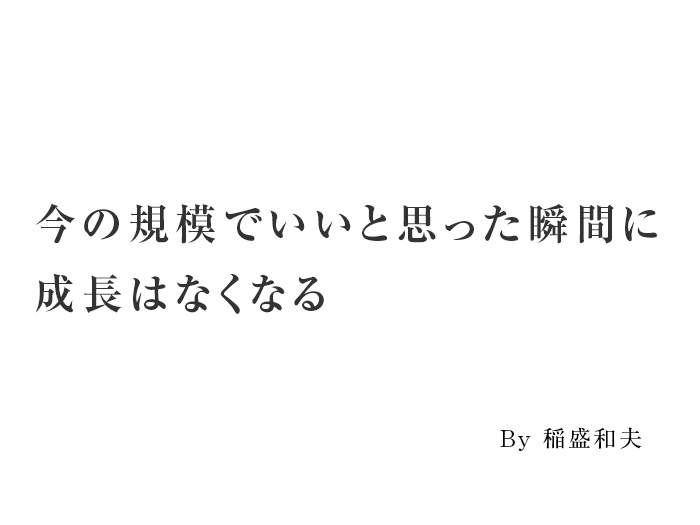
Vol.155 2024年11月号
2024年11月01日
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今年も残り2ヶ月となりましたね。
今月も元気に経営サポート隊通信をお届けいたします!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
今月は「致知」(2024年5月号)より93歳の現役料理人道場六三郎氏の
インタビューを抜粋してお届けします。
『冷蔵庫の使い方一つにしても工夫次第で差が出るんですよ。「あれ取って」と言われた時に、冷蔵庫をパッと開けてすぐ物を取り出して渡す。それができずに、「えっと、どこにあるんだっけ」とグズグズしていると、「バカ野郎」って言われてしまう。そこで、冷蔵庫の中を6つに仕切って整理整頓し、どこに何が入っているかメモを取り、扉に貼っておく。また、量が少なくなったら小さな容器に移し替え、冷蔵庫を広く使えるようにいつも心掛けていました。「軍人は要領を本文とすべし」と言われるように、段取りをきちんとしておけば、仕事が早く済むんです。スピード感がなくダラダラと働いているようじゃ使い物になりませんし、いつまでも仕事は上達しません。気づいたらすぐやる。面倒なことを先延ばしにしない。一気呵成にやることが仕事の鉄則です。(中略)これはよく言っていることですが、仕事にも人生にも締め切りがあります。ですから、常に先を見通して時間を無駄にせず、一つひとつの仕事をスピード感を持って仕上げていくことが大事ですね。僕は毎年、「今年はこれをできるようになろう」と目標を決め、それを必ずノートに書いて日々努力してきました。目標もなくダラダラと働いたり、人から言われた仕事だけを嫌々やったり、そういう姿勢では伸びていきません。
―道場さんにとって最大の逆境は何でしたか?
いろいろありましたけど、やっぱり最大の逆境、ターニングポイントはろくさん亭を開業する前、30代半ばで銀座の割烹「とんぼ」の料理長を務めていた時ですね。ある日、店の経営者が「道場さん、うちの重役になってくれ」と言うんですよ。「いいな」と思っていたら、「ちょっとお金を貸してくれないか」と。店は繁盛していましたので、僕は何の疑いもなくコツコツ貯金した500万円を全部下ろして、彼に貸しました。ところが、その一年後に会社が不渡りを出しましてね。後で分かったのは、方々から借り入れをして何とか店を経営していて、滞納していた売掛金もたくさんあったんです。彼は逃げちゃって貸したお金は一銭も返ってきませんでした。(中略)ほとほと困り果てた時に、「ああ、そうだ。僕にはお客様がいるんだ」と思って、僕ともう一人の債権者の共同経営という形で、同じビルの一階上のフロアに「新とんぼ」を開店しました。その時、保証金が2500万円くらい必要だったんですけど、大家さんが保証金なしで安い賃料で貸してくださったのは、実に有り難かったです。 おかげさまでとんぼ時代の常連さんをはじめ、開店当初からお客様がたくさん来てくださってね。一年目からちゃんと利益も出ていました。ただ、トップが2人いると指示系統も2つになって、店の内部に派閥が生まれ意見が割れてしまう。それで三年目に僕は自分の持っていた株を売って経営権を譲り、それを元手に銀座ろくさん亭を開店したんです。昭和46年、40歳の時でした。
空いていたビルの9階に出店したのですが、あの時代は飲食店といえば地下一階から地上二階までに出すのが通例でした。ビルの上階ではお客様が来ないだろうと。それでも僕は「惚れて通えば千里も一里」という諺のように、料理がおいしくてサービスもよければ、不利な条件であっても必ずお客様は来ると信念を持っていたんです。安い値段で出張料理を手掛けたり、一度でも来店してくれたお客様には季節ごとに必ず手紙を出したり、どうしたらお客様に来てもらえるのかをとにかく真剣に考え、一つひとつの料理やサービスの質を磨き高めていったんです。(中略)今振り返ると、普通ならコツコツ貯めた500万円を水の泡にして逃げた経営者を恨み、被害者意識の塊みたいになってもおかしくなかったと思います。だけど他人を恨んでもしょうがないし、自分で店をやっていける自信はありましたからね。きちんと調べもせずに軽率に貸した自分にも非がある。まあ、そう思ったのがよかったのでしょう。』いかがでしたか?私は「仕事にも人生にも締め切りがあります」ということばにハッとさせられました。仕事の締め切りは意識しても、日常的に人生の締め切りを意識することは少ないのではないでしょうか。続きは来月号に掲載いたします。
2024年10月の金言
2024年10月01日
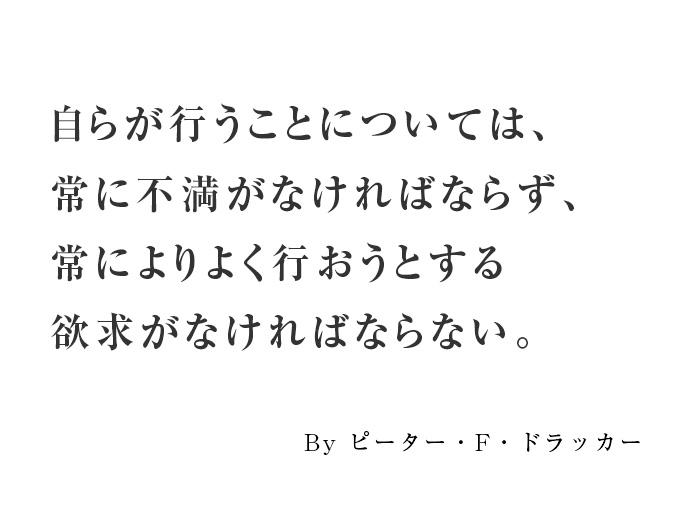
Vol.154 2024年10月号
2024年10月01日
今年も残り3ヶ月となりました。
皆さまお元気でお過ごしでしょうか?
今月も元気に経営サポート隊通信をお届けいたします!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
今月も、先月に引き続きプレジデントオンラインから元ソフトバンクホークス監督、
工藤公康氏の記事『なぜホークスを常勝軍団に替えられたのか…名監督・工藤公康が自分に課していた「選手への声掛け」ルール』をご紹介します。
『たとえばある選手が、昨日の試合でエラーをし、今日の挨拶後、私に守備面で不安を抱えていることを打ち明けてくれたとします。
その後、私はすぐ守備コーチに「彼とこんな話をしたよ」と報告するわけですが、そのやりとりを遠くから見ているその選手は、何を思うでしょうか。きっと「今、おれのことを話しているんだな。さっき話したこと以外に、何か話していないかな。もしかしたら『一度、二軍に落とそう』なんて話しているんじゃないだろうか……」なんて、気になって仕方がなくなるはずです。ならば初めから、コーチを含めて3人で話し、一度で話を終えるほうがいい。これが、私が導き出した結論です。本人がいないところで、その人の話をしない。チームの上層部と現場をつなぐ中間管理職である監督がオープンなコミュニケーションを心掛けることで、チーム内に「不要なモヤモヤ」が生まれづらくなります。
私が試合前に球場入りしたとき、挨拶をする順番は常に決まっていました。王会長がいらっしゃったら、王会長にまず挨拶をします。その後は近くにいる選手に声を掛けながらバッティングゲージのほうに向かい、そこで集まっている野手陣とコーチに挨拶。続いて、外野で準備運動をしている投手陣のもとに向かい、一人ひとりの選手とコーチに挨拶をします。孫オーナーがいらっしゃったらもちろん、真っ先に挨拶しますし、2018年以降は、王会長に挨拶した後は、コーチングアドバイザーとして加わった金星根さんに挨拶をするようにしたりと、自分より役職が上の方に対する挨拶の順番は細かく変わったりはしましたが、基本的には大きな流れが変わることはありませんでした。繰り返すと「まずは役職が上の方に挨拶→バッティングゲージのほうに向かう中で、近くにいる選手に挨拶→バッティングゲージの周りにいる野手陣・コーチに挨拶→外野にいる投手陣・コーチに挨拶」といった流れです。
選手の中で、とくに「この選手から挨拶する」といった優先順位はつけませんでした。ざっくばらんにいえば、さきほど述べたように「近くにいた選手から挨拶をする」という、本当にそれだけのことです。
ここにも、私なりの意図がありました。たとえば、ある選手のエラーが致命傷となり、前日の試合で負けてしまっていたとします。
今日の練習前、私が真っ先に、その選手に挨拶をしにいったら、彼はどう思うでしょうか。「ああ、おれが昨日ミスして試合に負けたから、監督はそれをずっと気にしていて、今日はまず、おれの様子をうかがいにきたんだな」と感じるでしょう。中には、「監督に気にかけてもらっている。今日は昨日のミスを取り返して、監督に心配かけないようにしよう」と意気に感じる選手もいるかもしれません。しかしそれでも、負けるたびに、その負けの原因をつくった選手から翌日に声をかけにいくのは、やはり異様でしょう。
それならば、前日の試合で活躍した選手から声をかければよいのか。そういうわけにもいきません。目に見えて活躍した選手を優先すると、目立たないプレーでチームに貢献している選手や、不調の選手が疎外感を持ちかねないからです。結局のところ、「近くにいた選手から順番に声をかける」がベストなのです。
私が選手とのコミュニケーションをとるのは、選手の「背景」を知るのが目的です。特定の選手と仲良くなるためではありません。
選手が自然に、自らの「背景」を話しやすい環境をつくるには、監督も自然に、「近くにいる人から声をかける」くらいの軽い意識で挨拶をしていたほうが、おそらくプラスに働きます。挨拶の順番に、下手に「意味」を持たせると、その「意味」を勘ぐられてしまうからです。』いかがでしたでしょうか?チーム作りのために、自然に振舞いながらも、繊細な気遣いと目的をもったコミュニケーションされている様子がよくわかりますね。
CATEGORY
ARCHIVE