2024年9月の金言
2024年09月02日
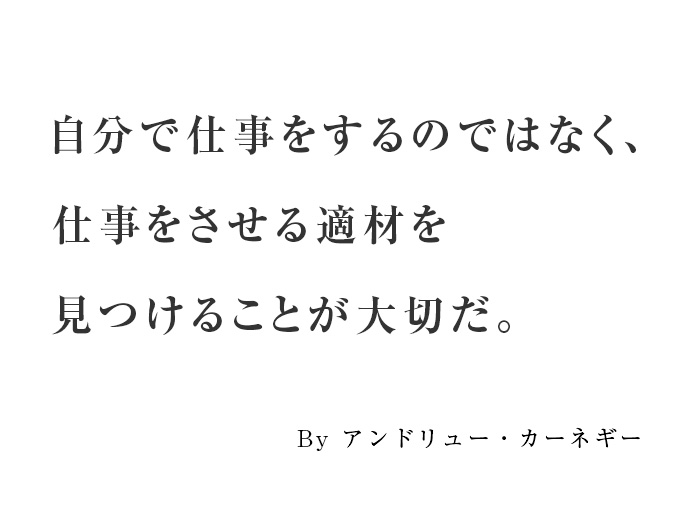
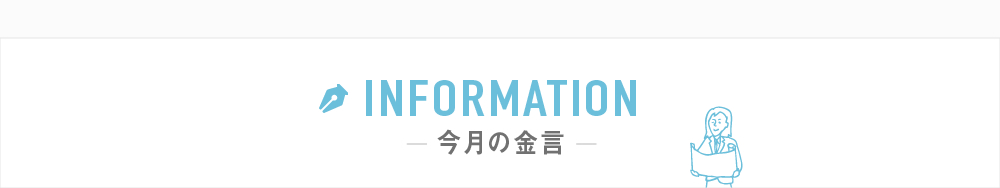
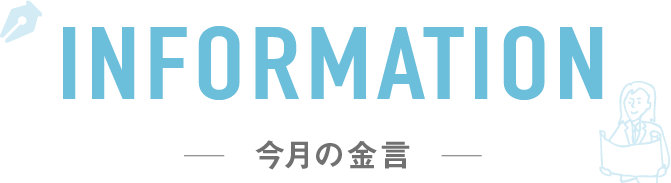
2024年9月の金言
2024年09月02日
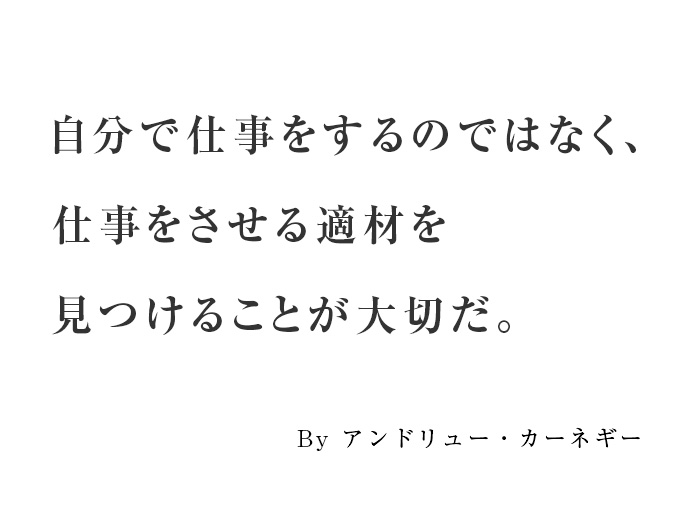
Vol.153 2024年9月号
2024年09月02日
9月の声を聴くと一気に秋めいた気分になりますね。
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今月も元気に経営サポート隊通信をお届けいたします!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
今月は、先月に引き続きプレジデントオンラインから元ソフトバンクホークス監督、
工藤公康氏の記事『なぜホークスを常勝軍団に替えられたのか…名監督・工藤公康が自分に課していた「選手への声掛け」ルール』をご紹介します。
『私がいくら「2016年シーズンの反省を踏まえて、コミュニケーションのあり方を考え直したんだ」と態度で示したところで、選手がいきなり心を開いてくれるはずもありません。そもそも、「選手の背景」とは、言い換えれば「選手のプライベート」でもあります。長い付き合いの友人や恋人、夫婦同士ならまだしも、さほど信頼関係を築けていない監督に対し、プライベートをさらけ出さなければいけない義理は、選手にはありません。どうしたら、選手は心を開いて、いろいろな背景を話してくれるようになるのか。考えた結果、「毎日の練習前、グラウンドで一人ひとりの選手に挨拶をしながら、『プラスひと声』をかけてみる」ようにしてみました。監督がいきなり「選手のことを知りたいから」と、一人ひとりを監督室に呼び出してじっくり話す時間をつくり出したら、選手もきっと「何事だ⁉」とビックリするでしょう。しかし、「グラウンドで挨拶をしがてら」なら、お互いそんなに気負うこともありません。それでも初めは慎重に、「挨拶プラスひと声」程度にとどめました。本当に簡単な、「今日も頑張れよ、頼むな」程度の、プラスひと声です。
毎日、「挨拶プラスひと声」の声掛けを続けていると、なんとなく、目の動きや表情の変化で、選手の心の揺れがわかるようになってきました。さきほどもお話ししたように、私がいくら気さくに話し掛けたところで、肩書きは「監督」であることに変わりなく、選手にとっては上司です。ある程度の「圧」は感じるであろうコミュニケーションですから、目をそらしたり、つくり笑顔が引きつったりといった、何らかの「サイン」は出やすくなります。
ある選手は、とてもわかりやすいサインを出してくれました。
調子がいいときは「おはようございます! 今日も頑張ります!」と明るい声で、まっすぐ私の目を見て挨拶してくれます。しかし調子の悪いときは、声こそ明るさを繕うのですが、目は伏し目がちになります。そして私が彼の前を去って次の選手に挨拶をしているとき、チラチラと私のほうを見てくるのです。いかにも「監督、もっと話したいことがあるのですが……」と言いたげな視線です。
そんなときは、全選手に挨拶をした後、その選手のところに戻って、ゆっくりと話す時間をとるようにしていました。
「挨拶プラスひと声」を続けることで、選手一人ひとりが放つサインを受けることができるようになり、だんだんと自身の「背景」を話してくれる選手も増えていきました。
さきほど私は、選手からの「不調のサイン」を受け取ったとき、「全選手に挨拶をした後にその選手のところに戻って、ゆっくりと話す時間をとるようにしていた」と述べました。その際、私はなるべく、コーチも交えて話すように心掛けていました。
理由は、「もしもコーチを交えなかったら、どのようなことが起きるか」を想像していただけるとわかりやすいでしょう。
まず、球団の組織図上、選手にとっていちばん近い相談相手はコーチであり、監督はそのコーチから相談を受ける立場です。監督が直接、選手と話し込んでいるのを担当コーチが見れば、「自分抜きで、何を話しているんだろう……」と気になるでしょう。私はもちろん、コーチのその気持ちを察して、選手とマンツーマンで話したことを、そのままコーチに伝えることになります。「さっきはこの選手がこんな相談をしてくれたから、こんなことを伝えたよ」と。気をつけなければいけないのは、ここです。』
選手の心情を考えて、どのようなタイミングでどのような声掛けをするか、またコーチをどのように巻き込むかなど、細かく気を遣いながらコミュニケーションをとっていった様子が語られています。この続きは来月号に掲載しますのでお楽しみに。
2024年8月の金言
2024年08月01日

Vol.152 2024年8月号
2024年08月01日
蒸し暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?
今月も元気に経営サポート隊通信をお届けいたします!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
今月はプレジデントオンラインから元ソフトバンクホークス監督、工藤公康氏の記事『なぜホークスを常勝軍団に替えられたのか…名監督・工藤公康が自分に課していた「選手への声掛け」ルール』をご紹介します。
『2016年に喫した、日本ハムファイターズに大逆転を許してのシーズン2位という結果。私はその失敗の原因を「自身のコミュニケーションの拙さ」にあると考えていました。2015年、就任1年目からリーグ優勝と日本一を果たしたことで、私は「自分のやり方は間違っていなかったのだ」という大きな自信を得ました。しかしその自信は、慢心へとつながることになります。2016年シーズンは、自分の中に少なからず、「私のやり方でやってください。このやり方で、去年も日本一になったじゃないですか。私の言うとおりにやれば勝てるんです」という気持ちがあったのも事実です。今から思えば、おごり以外の何物でもありません。自分でも知らず知らずのうちに、選手やコーチ、トレーナーに対して「私の言うとおりにやってくれればそれでいい」という一方通行のコミュニケーションを押し付けるようになっていたのでした。その年のシーズンオフ。私は反省し、チーム内でのコミュニケーションのあり方を根本から考え直すことになります。ここからは、私がコミュニケーションのあり方をどのように考え直し、実行したかを、具体的にお話ししていきます。
まずお話ししておきたいのは、私は決して、「監督と選手は、何が何でもとことん対話すべきだ」とは考えていないということです。もしかしたら、「普段はあまり選手とコミュニケーションを交わさず、でもいざというときに的確な声を掛けることで、選手のモチベーションやポテンシャルを引き出す」という監督の形もあるのかもしれません。ただ、2016年当時の私には、「選手とどのようにコミュニケーションをとるのが、勝ち続けるチームをつくり上げるために有効なのか」というノウハウがまったくありませんでした。私の中にあったのは、「とにかく今のままではいけない。コミュニケーションのあり方を改めないといけない」という気持ちだけです。ここで記すのは、そんな私が、必死にもがきながらなんとか見出したコミュニケーションです。コミュニケーションのあり方を改めるにしても、どう改めるのか。私が思い至ったのは、「まず、選手のことをもっと知らなければ」ということでした。
就任してから2年目を終えるまでも(つまり私が「コミュニケーションのあり方を考え直さなければ」と思い知る以前も)、私は選手たちに、「話したいことがあったら、いつでも遠慮なく声を掛けてね」とは伝えていました。「選手たちと密にコミュニケーションをとりたい」という気持ち自体は持っていたのです。しかし、進んで私とコミュニケーションをとりにきてくれる選手はごくわずかでした。考えてみれば当然です。こちらがいくら「ウェルカム」の姿勢を示しても、監督は監督。選手にとってみれば上司であり、気を遣う存在です。好き好んで本心を話しにきてくれる選手は、そうそういません。「話したいんだったらきていいよ」という「待ち」のコミュニケーションでは、「選手を知る」という目的は果たせないのです。また、就任当初の2年間は、私のやり方を押し付けていたこともあり、内心で「なんなんだこの監督は」と思われて避けられていた部分もあったのかもしれません。私は、「選手を知るには、監督である自分から、選手に声を掛けて話を聞かなければならないのだ」と考えました。私は選手の何を知りたいと思ったのか。それは、選手の「背景」です。プロ野球選手としての生き方や、練習への姿勢、試合に懸ける思いには、選手の背景が大きく影響します。いつから野球を始めたのか。学生時代はどんなチームでプレーしていたのか。どのようなポジションを守る、どのような打者だったのか。出身地はどこなのか。どのような家族のもとで生まれ育ったのか。どのような性格なのか。奥さまはどのような人で、どのような家庭を築いているのか。日々の生活の中で大切にしていることは何か。今、困っていることは何か。どのような夢を持っているのか。このような、選手の「背景」をひとつでも多く知ることができれば、練習や試合の中で、その選手に合う環境を整えることができ、試合でより高いパフォーマンスを発揮してくれるのではないか。私はそう考えたのです。』
工藤氏がコミュニケーションの取り方を意識的に変えていったことが、具体的にわかります。自己の慢心が招いた監督2シーズン目の大逆転の結果2位。反省した工藤氏は自らを省み、変わっていきます。続きは来月にお届けいたします
2024年7月の金言
2024年07月01日
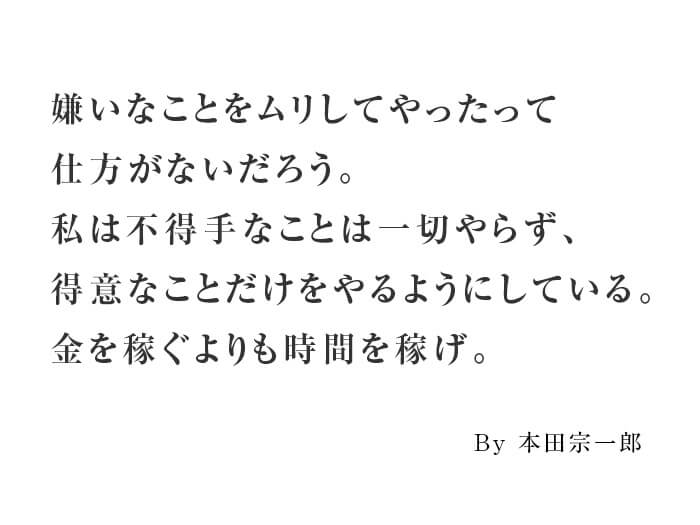
Vol.151 2024年7月号
2024年07月01日
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今月も元気に経営サポート隊通信をお届けいたします!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
今月も、先月に引き続き日経ビジネス電子版の記事からお届けします。(「なぜそれを知っている?」顧客を驚かせる会社キーエンス」2023.10.16西岡杏(日経ビジネス記者))
『「こんなに簡単なんですか? 初見で使えますね!」。「ガーナ」などのチョコレートを製造するロッテ浦和工場(さいたま市)。生産技術の担当者は2018年、キーエンス製の画像センサーの導入を決めた。工場に持ち込まれたデモ機を見るだけで、設定のシンプルさが分かったからだ。
それまでロッテの担当者が悩んでいたのは、検査工程の歩留まりの悪さ。チョコレートの「割れ」や「欠け」を判別する装置を用いていたが、精度が足りずに良品まではじいてしまう状況だった。
そこに声をかけたのが、毎月のように工場を来訪するキーエンスの営業担当者だった。ロッテの担当者は「相談を持ちかけると喜んで応じてくれ、翌週には具体的な提案に仕上げてくるようなスピード感がある」とその姿勢に好感を持った。そして、実際に持ち込んできた提案は、ロッテの想像を超えていた。
歩留まりの悪さという問題の解決に特化するのであれば、判別精度が高い装置に置き換えるのが近道だろう。ところがキーエンスの営業担当者が出してきたのは、高精度にするだけでなく、使いやすさを重視する提案だった。
多くの製造現場では、複雑な装置を作業者が使いこなせず、宝の持ち腐れになっている。「調整が難しい機械は、次第に敬遠されるようになる」。営業担当者はこうした実情をよく理解しているように見えた。
「一握りの専門家だけで考えるのではなく、生産ラインに関わる多くの人の知恵を結集して歩留まりを高めたい」。ロッテが抱えていたそんなニーズを先回りして具体化し、目の前に示したからこそ、キーエンスは自社商品の導入につなげられたわけだ。
先回りして本質を探り当てて解決すれば、大きな価値を提供できる。顧客も気づかない潜在需要こそ、キーエンスにとっては宝の山なのだ。それは、米アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズ氏が「人は形にして見せてもらうまで自分は何が欲しいか分からない」と喝破したのと通じる。
電子部品の雄、村田製作所の中島規巨社長は取引先であるキーエンスの力に脱帽する。「あの会社の付加価値は、もう人。彼らのすごい提案力です。うちの設備を開発している者たちもコロッとやられるんです」
国内トップ3の時価総額、メーカーとして驚異の利益率、そして上場企業の中で屈指の高賃金。キーエンスを表す数字は、日本企業としては突出したものばかりだ。
なぜキーエンスはそれができるのか。その疑問に端的に答えたのが、「キーエンスは仕組みと、それをやり切る風土がすごい」というキーエンスOBの指摘だろう。属人的な意欲や能力に頼ることなく顧客に与える価値を最大化できるように仕組みを整備し、社員はその仕組みに合わせて正しい行動をやり切る。それがキーエンスの強さの根源であり、人材育成の要諦でもある。』
いかがでしたでしょうか?3ヶ月に渡りお届けしましたキーエンスの記事、一人一人はスーパーマンではないけれど、コミュニケーションを着実にして、システム化していくことでチームとして、可能性のある顧客を全て拾っていき、顧客の問題を解決することにより、さらに次の顧客につなげる。資金の多寡の問題ではなく、本気で顧客の問題解決に取り組むことが、いまのキーエンスの発展につながっていると実感した記事でした。
CATEGORY
ARCHIVE