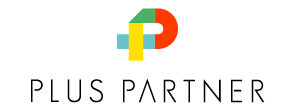Vol.151 2024年7月号
2024年07月01日
皆さまいかがお過ごしでしょうか?
今月も元気に経営サポート隊通信をお届けいたします!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
今月も、先月に引き続き日経ビジネス電子版の記事からお届けします。(「なぜそれを知っている?」顧客を驚かせる会社キーエンス」2023.10.16西岡杏(日経ビジネス記者))
『「こんなに簡単なんですか? 初見で使えますね!」。「ガーナ」などのチョコレートを製造するロッテ浦和工場(さいたま市)。生産技術の担当者は2018年、キーエンス製の画像センサーの導入を決めた。工場に持ち込まれたデモ機を見るだけで、設定のシンプルさが分かったからだ。
それまでロッテの担当者が悩んでいたのは、検査工程の歩留まりの悪さ。チョコレートの「割れ」や「欠け」を判別する装置を用いていたが、精度が足りずに良品まではじいてしまう状況だった。
そこに声をかけたのが、毎月のように工場を来訪するキーエンスの営業担当者だった。ロッテの担当者は「相談を持ちかけると喜んで応じてくれ、翌週には具体的な提案に仕上げてくるようなスピード感がある」とその姿勢に好感を持った。そして、実際に持ち込んできた提案は、ロッテの想像を超えていた。
歩留まりの悪さという問題の解決に特化するのであれば、判別精度が高い装置に置き換えるのが近道だろう。ところがキーエンスの営業担当者が出してきたのは、高精度にするだけでなく、使いやすさを重視する提案だった。
多くの製造現場では、複雑な装置を作業者が使いこなせず、宝の持ち腐れになっている。「調整が難しい機械は、次第に敬遠されるようになる」。営業担当者はこうした実情をよく理解しているように見えた。
「一握りの専門家だけで考えるのではなく、生産ラインに関わる多くの人の知恵を結集して歩留まりを高めたい」。ロッテが抱えていたそんなニーズを先回りして具体化し、目の前に示したからこそ、キーエンスは自社商品の導入につなげられたわけだ。
先回りして本質を探り当てて解決すれば、大きな価値を提供できる。顧客も気づかない潜在需要こそ、キーエンスにとっては宝の山なのだ。それは、米アップルの創業者であるスティーブ・ジョブズ氏が「人は形にして見せてもらうまで自分は何が欲しいか分からない」と喝破したのと通じる。
電子部品の雄、村田製作所の中島規巨社長は取引先であるキーエンスの力に脱帽する。「あの会社の付加価値は、もう人。彼らのすごい提案力です。うちの設備を開発している者たちもコロッとやられるんです」
国内トップ3の時価総額、メーカーとして驚異の利益率、そして上場企業の中で屈指の高賃金。キーエンスを表す数字は、日本企業としては突出したものばかりだ。
なぜキーエンスはそれができるのか。その疑問に端的に答えたのが、「キーエンスは仕組みと、それをやり切る風土がすごい」というキーエンスOBの指摘だろう。属人的な意欲や能力に頼ることなく顧客に与える価値を最大化できるように仕組みを整備し、社員はその仕組みに合わせて正しい行動をやり切る。それがキーエンスの強さの根源であり、人材育成の要諦でもある。』
いかがでしたでしょうか?3ヶ月に渡りお届けしましたキーエンスの記事、一人一人はスーパーマンではないけれど、コミュニケーションを着実にして、システム化していくことでチームとして、可能性のある顧客を全て拾っていき、顧客の問題を解決することにより、さらに次の顧客につなげる。資金の多寡の問題ではなく、本気で顧客の問題解決に取り組むことが、いまのキーエンスの発展につながっていると実感した記事でした。