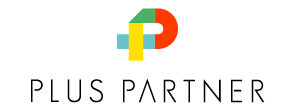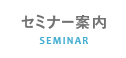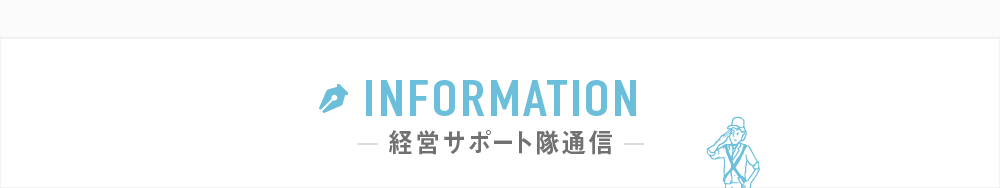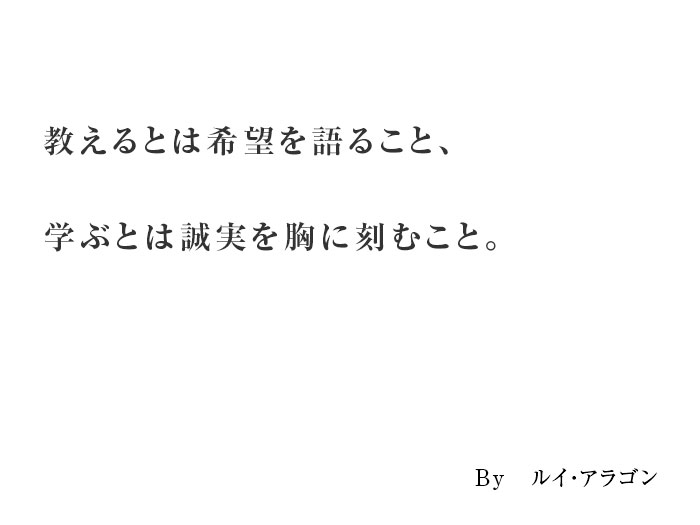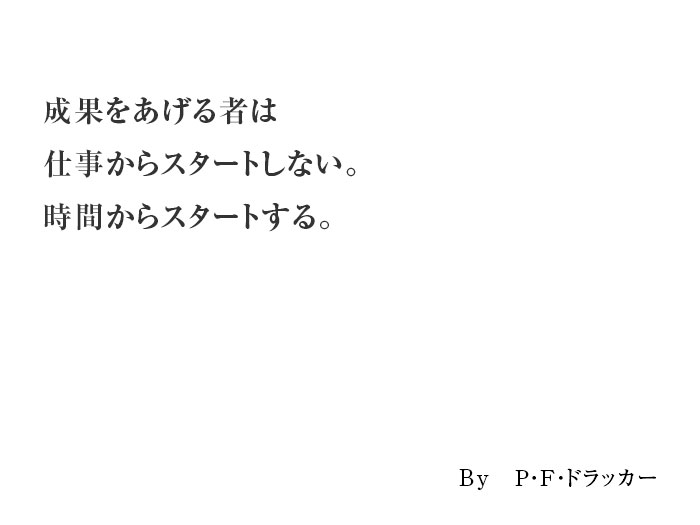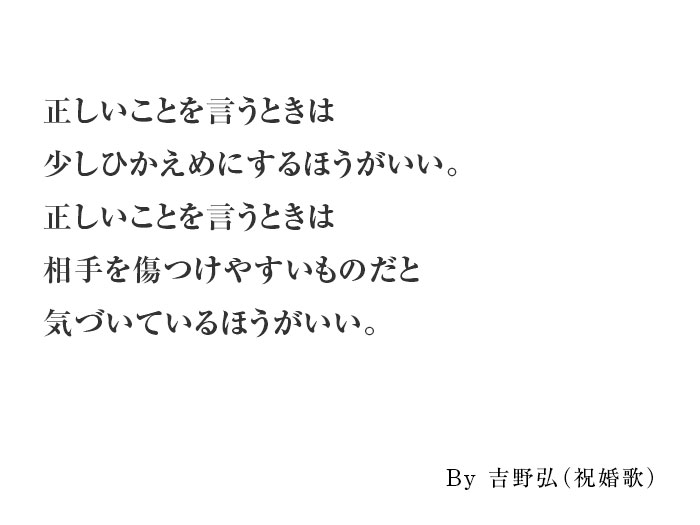Vol.54 2016年6月号
2016年06月20日
こんにちは!!
梅雨のジメッとした季節になりましたが、
皆さまお元気でお過ごしでしょうか?
今月も経営サポート隊通信をお届け致します!
【河合由紀子のちょっとイイ話】
先日、ビジネス文書について改めて勉強する機会がありました。知っているようで知らないことが多く、反省することもたくさんありました。
また、現代社会ならではの落とし穴にも気づかされました。昔は上司に印鑑をもらわなければ社外に文書を出すことができませんでしたが、現在はメールなどで社外に文書を直接出すことが多くなっています。これは、つまりビジネス文書の書き方について、鍛えられる機会が少なくなっているということです。しかし、会社や組織の名称をつけて社外に出す文書は、社内の承認を得ていなくても、対外的には「公式」の文書と位置付けられます。うっかり恥ずかしい文書が外に出てしまわないよう、より一層ビジネス文書に関する教育が必要だと感じました。
ビジネス文書の考え方は「短く・易しく・正確に」ということです。
一文の長さは、40~50字程度、一段落は100~120字程度を目安にすると読みやすいようです。
また、漢字は「常用漢字」が原則で、全体として漢字の率は30%台が一般的です。ちなみに、新聞は37%前後ですので、そのくらいの感覚に目が慣れているということです。
他にも、ダブリは下品な感じを与えるので注意が必要です。例えば、「~だけに限る」→「~に限る」、「過保護すぎる」→「保護しすぎる」、「約1時間ぐらい」→「約1時間」などです。ついつい使ってしまっていることがあるかもしれません。
他にも、『「殿」「様」論議』というものがあります。昭和27年の国語審議会では、『①「さん」を標準のかたちとする、②「さま(様)」はあらたまった場合のかたち、また慣用語に見られるが、主として手紙の宛名に使う、③将来は、公用文の「殿」も「様」に統一されることが望ましい』とされています。つまり、「殿」は国や地方公共団体が職務上作成するものに使われ、その他はビジネス文書では「様」を使うのが一般的ということです。
とにかく迷った時は、現在国が何を標準と定めているのかを知ることにより、判断することができます。なぜなら、時代により日本語は変わっているからです。ただ、標準を知らずに我流でビジネス文書を作成すると、危険を伴うということですね。